
人気ドッグトレーナー/訓練士
愛するワンちゃんとの別れは、飼い主にとって最も辛い経験の一つです。しかし、最期の時が近づいているサインを理解しておくことは、ワンちゃんが穏やかに旅立てるように寄り添い、後悔のないお別れをするために非常に大切です。
愛犬が老衰や病気・怪我により死を迎える時期はいづれ訪れます。この時期、犬は特有の行動やサインを示すことがあります。
例えば、犬が死ぬ前に見られる行動には、寝ないことや甘えること、さらには悲鳴を上げることなどがあります。また、犬の体から発せられる臭いや、舌を出している姿も、彼らの状態を示す重要なサインです。
本記事では、犬が死ぬ前に見られる行動について解説し、飼い主としての心構えや対応について考えていきます。愛犬との最後の時間を大切にするために、これらのサインをしっかりと理解しておきましょう。
犬が死ぬ前の行動とその理由

愛犬の最期が近づくと、これまで見られなかったような行動の変化が現れることがあります。体力の低下や内臓機能の衰え、そして精神的な変化により、犬が本能的に示すサインです。
例えば、急に落ち着きがなくなってウロウロしたり、逆にほとんど動かなくなったりすることがあります。また、これまでできていたことができなくなることへの不安から、普段はしないような行動をとることもあります。
犬が死ぬ前に寝ない理由:眠れない様子が見られたら

最期が近づくと、犬は体力の低下や痛み、不快感などから、うまく眠れなくなることがあります。夜中に何度も起きて徘徊したり、呼吸が苦しそうで横になれなかったりする様子が見られるかもしれません。また、精神的な不安から落ち着かず、眠れない場合もあります。
もし愛犬が眠れない様子を見せている場合は、体を優しく撫でて安心させてあげたり、静かで落ち着ける環境を用意してあげたりすることが大切です。痛みが原因と考えられる場合は、獣医師に相談して適切な処置を受けるようにしましょう。
- 不安やストレス
- 犬が死ぬ前に寝ない場合、体調の変化や痛み、不安感からくるストレスが影響していることがあります。特に、老犬や病気を抱えた犬は、体の不調を感じることで不安を抱き、落ち着いて眠ることができなくなることがあります。
- 痛みの感覚
- 痛みや不快感があると、犬はリラックスできず、眠ることが難しくなります。特に、がんや内臓疾患などの病気を抱えている場合、痛みが強くなることがあり、その結果、犬は寝ることを避けることがあります。
- 生理的な変化
- 犬が死ぬ前には、体の生理的な変化が起こります。これには、ホルモンバランスの変化や代謝の低下が含まれます。これらの変化は、犬のエネルギーレベルや睡眠パターンに影響を与え、通常の睡眠サイクルが乱れることがあります。
- 飼い主との絆
- 犬は飼い主との強い絆を持っています。死が近づくと、犬は飼い主のそばにいたいと感じることが多く、安心感を求めて寝ることを避けることがあります。特に、飼い主が近くにいるときは、犬は安心して眠ることができない場合があります。
- 本能的な行動
- 犬は本能的に危険を察知する能力を持っています。死が近づくと、犬は自分の状態を理解し、周囲の環境に対して敏感になることがあります。このため、警戒心が高まり、眠ることができなくなることがあります。
- 環境の影響
- 犬が寝るためには、静かで安心できる環境が必要です。周囲の騒音やストレス要因があると、犬はリラックスできず、眠ることが難しくなります。特に、病院や見知らぬ場所にいる場合、環境が犬にとってストレスとなり、眠れないことがあります。
犬が死ぬ前に寝ない理由は、身体的な不調や心理的な要因、環境の影響など、さまざまな要素が絡み合っています。飼い主は、愛犬の状態を注意深く観察し、必要に応じて獣医に相談することが重要です。また、犬が安心できる環境を整え、できるだけストレスを軽減することが、犬の最期を穏やかに過ごさせるために大切です。
死ぬ前の犬の臭いの変化:体臭の変化に気づいたら

死期が近づくと、犬の体臭が変化することがあります。これは、内臓機能の低下や代謝の変化、あるいは腫瘍などの病気が原因となっている可能性があります。また、老衰によって免疫力が低下し、感染症を引き起こしている場合も考えられます。
もし愛犬の体臭に異変を感じたら、自己判断せずに獣医師に相談することが重要です。原因を特定し、適切なケアを行うことで、愛犬の苦痛を和らげることができるかもしれません。
- 体内の化学変化
- 犬が死に近づくと、体内でさまざまな化学変化が起こります。これには、内臓の機能低下や代謝の変化が含まれます。特に、肝臓や腎臓の機能が低下すると、体内に毒素が蓄積され、これが体臭に影響を与えることがあります。これにより、通常とは異なる、強い臭いを発することがあります。
- 皮膚の変化
- 犬が死ぬ前には、皮膚の状態も変化します。皮膚が乾燥したり、剥がれたりすることがあり、これが臭いの原因となることがあります。また、皮膚の感染症や病気が進行している場合、膿や腐敗臭が発生することもあります。
- 呼吸の変化
- 犬が死に近づくと、呼吸のパターンが変わることがあります。呼吸が浅くなったり、苦しそうな呼吸をすることがあり、これが口臭や体臭に影響を与えることがあります。特に、口腔内の健康状態が悪化している場合、口臭が強くなることがあります。
- 食欲の低下
- 死が近づくと、犬の食欲が低下することが一般的です。食べ物を摂取しないことで、消化器系の活動が減少し、体内の老廃物が蓄積されることがあります。これにより、体臭が変化し、通常とは異なる臭いを発することがあります。
- 感染症や病気の影響
- 犬が病気を抱えている場合、特に感染症やがんなどの重篤な病気が進行していると、特有の臭いを発することがあります。これらの病気は、体内での炎症や腐敗を引き起こし、強い臭いを伴うことがあります。
- 精神的な要因
- 犬は感情やストレスに敏感な動物です。ストレスや不安が高まると、体の化学反応が変化し、臭いにも影響を与えることがあります。特に、飼い主との絆が強い犬は、飼い主の感情を感じ取り、ストレスを感じることがあり、これが臭いに反映されることがあります。
犬が死ぬ前の臭いの変化は、身体的な健康状態や生理的な変化、環境要因など、さまざまな要因によって引き起こされます。飼い主は、愛犬の臭いの変化に気づいた場合、獣医に相談し、適切なケアを行うことが重要です。また、愛犬が快適に過ごせるように、環境を整えることも大切です。
犬が死ぬ前に挨拶をする行動:別れを告げるような行動

犬は、言葉を話せませんが、行動を通して私たちに様々なメッセージを伝えてくれます。最期が近づくと、まるで別れを告げるかのように、飼い主の顔をじっと見つめたり、体を擦り寄せたり、普段はしないような特別な行動を見せることがあります。
これは、愛犬が飼い主への感謝の気持ちや、別れを惜しむ気持ちを表しているのかもしれません。このような行動が見られたら、優しく声をかけ、撫でてあげるなど、愛情をたっぷりと伝えてあげてください。
- 終末期の本能的な行動
- 犬は本能的に群れで生活する動物であり、飼い主との絆が非常に強いです。死が近づくと、犬は自分の状態を理解し、最後の瞬間を大切にしようとすることがあります。このため、飼い主に挨拶をすることで、感謝の気持ちや愛情を伝えようとしていると考えられます。
- 飼い主との絆の確認
- 犬は飼い主との強い絆を持っています。死が近づくと、犬はその絆を再確認し、最後の瞬間を共有したいと感じることがあります。挨拶をすることで、飼い主に対する愛情や信頼を示し、安心感を得ようとしているのかもしれません。
- 不安やストレスの表れ
- 犬が死に近づくと、身体的な不調や痛みを感じることが多く、これが不安やストレスを引き起こすことがあります。飼い主に挨拶をする行動は、飼い主に対する依存や安心感を求める表れである可能性があります。飼い主のそばにいることで、少しでも安心感を得ようとしているのかもしれません。
- 最後の別れの準備
- 犬は直感的に自分の状態を理解することができる動物です。死が近づくと、犬は自分の最後の瞬間を意識し、飼い主に別れを告げるために挨拶をすることがあります。この行動は、犬が自分の死を受け入れ、飼い主に感謝の気持ちを伝えようとしていると解釈されることがあります。
- 行動の変化
- 犬が死ぬ前には、普段とは異なる行動を示すことがあります。例えば、普段は元気な犬が急に静かになったり、逆に普段はおとなしい犬が活発になることがあります。これらの行動の変化は、犬が自分の状態を理解し、飼い主に対して特別なメッセージを伝えようとしている可能性があります。
犬が死ぬ前に飼い主に挨拶をする行動は、愛情や感謝の表れであり、飼い主との絆を再確認するためのものと考えられます。また、犬が不安やストレスを感じている場合もあり、飼い主の存在が安心感を与えることがあります。飼い主は、愛犬の行動に注意を払い、最後の瞬間を大切に過ごすことが重要です。
死ぬ前に甘える:いつも以上に飼い主を求める犬の心理

不安や心細さを感じている犬は、最期が近づくと、いつも以上に飼い主に甘えるようになることがあります。そばを離れようとしなかったり、抱っこをせがんだり、体をぴったりとくっつけてきたりするかもしれません。
これは、飼い主の温もりや安心感を求めているサインです。できる限り愛犬のそばにいて、優しく撫でたり、声をかけたりして、安心させてあげてください。
- 安心感の追求
- 犬は本能的に群れで生活する動物であり、飼い主との絆が非常に強いです。死が近づくと、犬は不安や恐怖を感じることが多くなります。このため、飼い主に甘えることで安心感を得ようとするのです。飼い主のそばにいることで、心の安定を求めていると考えられます。
- 愛情の表現
- 犬は感情豊かな動物であり、愛情を示すために甘える行動を取ります。死が近づくと、犬は自分の感情を強く表現し、飼い主に対する愛情を伝えようとすることがあります。この甘える行動は、最後の瞬間に愛情を確認し合うための手段とも言えます。
- 最後の別れの準備
- 犬は直感的に自分の状態を理解することができる動物です。死が近づくと、犬は自分の運命を受け入れ、飼い主に最後の別れを告げるために甘えることがあります。この行動は、犬が自分の死を意識し、飼い主に感謝の気持ちを伝えようとしていると解釈されることがあります。
- 身体的な不調のサイン
- 犬が死ぬ前には、身体的な不調や痛みを感じることが多くなります。甘える行動は、飼い主に助けを求めるサインである場合もあります。犬は痛みや不快感を和らげるために、飼い主のそばに寄り添い、甘えることで安心感を得ようとしているのかもしれません。
- 社会的な絆の強化
- 犬は社会的な動物であり、群れの一員としての役割を持っています。死が近づくと、犬は自分の存在を確認し、飼い主との絆を強化しようとすることがあります。甘えることで、飼い主との関係を再確認し、最後の瞬間を共に過ごすことを望んでいるのかもしれません。
犬が死ぬ前に甘える行動は、安心感を求めるためや愛情を表現するため、さらには身体的な不調を和らげるための手段として現れることがあります。飼い主は、愛犬のこのような行動に敏感になり、最後の瞬間を大切に過ごすことが重要です。犬との絆を深め、愛情を持って接することで、犬にとっても飼い主にとっても心温まる時間を共有することができるでしょう。
死ぬ前の犬の悲鳴の意味:苦しそうな声や鳴き声

最期が近づくと、犬が苦痛や呼吸困難などによって、悲鳴のような声を上げたり、うめき声や鳴き声をあげたりすることがあります。これは、愛犬が非常に苦しい状態にあることを示している可能性が高いです。
もし愛犬が苦しそうな声を上げている場合は、すぐに獣医師に連絡を取り、指示を仰いでください。可能な限り早く動物病院を受診し、適切な処置を受けることが重要です。
- 身体的な痛みや不快感
- 犬が死ぬ前に悲鳴を上げる最も一般的な理由は、身体的な痛みや不快感です。病気や怪我、老化による痛みが原因で、犬は苦しみを感じることがあります。このような場合、悲鳴は痛みを表現する手段となります。飼い主は、犬の状態を注意深く観察し、必要に応じて獣医に相談することが重要です。
- 不安や恐怖
- 死が近づくと、犬は不安や恐怖を感じることがあります。特に、孤独感や周囲の変化に対する恐れが強くなると、悲鳴を上げることがあります。このような場合、犬は飼い主に助けを求めている可能性があります。飼い主がそばにいて安心感を与えることで、犬の不安を和らげることができるかもしれません。
- コミュニケーションの一環
- 犬は感情を表現するために様々な音を使います。悲鳴は、犬が何らかの感情を伝えようとしているサインであることもあります。例えば、飼い主に対する愛情や、最後の別れを告げるためのコミュニケーションとして悲鳴を上げることがあります。この場合、犬は自分の気持ちを伝えようとしているのかもしれません。
- 生理的な反応
- 犬が死ぬ前には、身体がさまざまな生理的な変化を経験します。これに伴い、呼吸が乱れたり、心拍数が変化したりすることがあります。これらの変化がストレスや不快感を引き起こし、悲鳴として表れることがあります。特に、呼吸困難や心臓の問題がある場合、犬は悲鳴を上げることがあるため、注意が必要です。
- 最後のサイン
- 犬が死ぬ前に悲鳴を上げることは、最後のサインであることもあります。犬は直感的に自分の状態を理解することができるため、死が近づくとその感情を表現するために悲鳴を上げることがあります。この場合、飼い主は犬の気持ちを理解し、最後の瞬間を大切に過ごすことが求められます。
犬が死ぬ前に悲鳴を上げる理由は、身体的な痛みや不安、コミュニケーション、生理的な反応、そして最後のサインなど、さまざまな要因が考えられます。飼い主は、愛犬の状態を注意深く観察し、必要に応じて適切な対応をすることが重要です。犬との絆を深め、愛情を持って接することで、犬にとっても飼い主にとっても心温まる時間を共有することができるでしょう。
舌を出す犬の行動とその意味:ぐったりとした様子と合わせて注意

犬がぐったりとして動かない状態で舌が出ている場合は、体力が極度に低下している、あるいは意識が朦朧としている可能性があります。また、呼吸困難を起こしている場合や、熱中症などの緊急性の高い状態も考えられます。
もし愛犬がぐったりとして舌が出ている場合は、すぐに獣医師に連絡を取り、状況を説明してください。特に呼吸が苦しそうな場合は、一刻も早く動物病院を受診する必要があります。
- 呼吸困難や苦痛のサイン
- 犬が死に近づくと、体の機能が低下し、呼吸が困難になることがあります。この場合、犬は舌を出してハアハアと呼吸することが多くなります。これは、体内の酸素を確保しようとする自然な反応です。特に、心臓や肺に問題がある場合、舌を出すことで苦しさを和らげようとすることがあります。
- 体温調節の失敗
- 死に近づくと、犬の体温調節機能が正常に働かなくなることがあります。これにより、犬は舌を出して体温を下げようとすることがありますが、効果がない場合もあります。このような状況では、犬が非常に弱っていることを示すサインとなります。
- 意識の低下
- 犬が死に近づくと、意識が朦朧とすることがあります。この状態では、犬は自分の体をうまくコントロールできず、舌を出したままになることがあります。これは、犬が自分の状態を理解できず、無防備な状態にあることを示しています。
- ストレスや不安
- 犬が死に近づくと、ストレスや不安を感じることがあります。この場合、舌を出すことは、犬が不安を感じているサインであることがあります。特に、飼い主がそばにいるときにこの行動が見られることがあります。
- 病気や老化の影響
- 老犬や病気の犬は、舌を出すことが多くなることがあります。これは、筋力の低下や口の中の問題、または全体的な健康状態の悪化が原因であることがあります。特に、末期の病気にかかっている犬は、舌を出すことが多くなる傾向があります。
犬が死ぬ前に舌を出す行動は、さまざまな要因によって引き起こされることがあります。呼吸困難や体温調節の失敗、意識の低下、ストレス、病気や老化の影響などが考えられます。飼い主は、犬の行動を注意深く観察し、必要に応じて獣医に相談することが重要です。犬が苦しんでいる場合、適切なケアやサポートを提供することが大切です。
老衰と犬の死ぬ間際の行動

若い犬が病気や事故によって突然亡くなるケースとは異なり、老犬の場合は、長い年月を経て徐々に体の機能が衰えていく中で最期を迎えることが多いです。
老衰による死は、一般的に緩やかな経過をたどります。若い頃のように活発に動き回ることが少なくなり、寝ている時間が増え、食欲も徐々に低下していきます。視力や聴力も衰え、これまでできていた日常的な動作にも時間がかかるようになるでしょう。
- 食欲の低下
- 老衰が進むと、犬は食欲を失うことがよくあります。これは、体がエネルギーを必要としなくなり、消化器系の機能が低下するためです。飼い主は、食事を取らないことが続く場合、獣医に相談することが重要です。
- 活動量の減少
- 犬が老衰により死ぬ間際には、普段のように活発に動くことが少なくなります。散歩や遊びを嫌がるようになり、寝ている時間が増えることが一般的です。このような行動は、体力の低下や痛みを感じていることを示しているかもしれません。
- 社会的な接触の変化
- 犬は通常、飼い主や他のペットと交流を持ちますが、老衰が進むと、他者との接触を避けることがあります。これは、体調が優れないために他者と関わることが負担に感じるからです。一方で、甘えたがる行動が見られることもあります。
- 排泄の変化
- 老衰に伴い、排泄の頻度や状態が変わることがあります。尿や便のコントロールが難しくなったり、排泄の場所を間違えたりすることがあるため、飼い主は注意深く観察する必要があります。
- 呼吸の変化
- 犬が死ぬ間際には、呼吸が浅くなったり、速くなったりすることがあります。また、呼吸が不規則になることもあります。これらの変化は、体が弱っていることを示す重要なサインです。
- 体温の変化
- 老衰が進むと、犬の体温が低下することがあります。特に、手足が冷たくなることが多く、これは血液循環が悪くなっていることを示しています。
- 目の輝きの変化
- 犬の目は、健康状態を反映する重要な部分です。老衰が進むと、目の輝きが失われ、無表情になることがあります。これは、犬が痛みや不快感を感じている可能性を示唆しています。
老衰で最期を迎える犬にとって、最も大切なことは「穏やかで苦痛のない時間を過ごせるようにすること」です。愛犬の様子を注意深く観察し、できる限りのケアをしてあげましょう。必要に応じて獣医の助けを求めることも大切です。
老衰による自然な衰弱は、病気などによる急激な変化とは異なり、時間をかけてゆっくりと進行します。長年共に過ごした愛犬の体が少しずつ衰えていく様子を見るのは辛いものですが、これは自然な生命のサイクルであり、避けることのできない過程です。
まとめ
~死ぬ前の犬にできること~

愛犬が最期の時を迎えるにあたって、飼い主として何ができるのか、どのように寄り添うべきか…?最も大切なことは「愛犬が穏やかで安らかに旅立てるように、愛情と配慮をもってサポートすること」です。
この時間は、飼い主にとっても非常に辛いものですが、愛犬にとっては、飼い主の愛情を感じながら穏やかに旅立つことが何よりも大切です。できる限りの愛情を注ぎ、後悔のないお別れができるように、精一杯寄り添ってあげてください。
最期の時間を安らかに過ごせるように
- 快適な環境を整える
- 愛犬がリラックスできる静かで落ち着いた場所を用意しましょう。柔らかいベッドや毛布を用意し、温度管理にも気を配ってください。
- 体勢を楽にする
- 自力で体勢を変えるのが難しい場合は、定期的に体位を変えてあげ、床ずれを防ぎましょう。クッションなどを利用して、呼吸が楽な体勢を保てるように工夫するのも大切です。
- 清潔を保つ
- 体が汚れていたり、排泄物が付着していたりする場合は、優しく拭いてあげましょう。清潔な状態は、愛犬の安楽につながります。
- 水分補給をサポートする
- 自力で水を飲めない場合は、スポイトやシリンジを使って少しずつ水分を与えてみましょう。ただし、無理に飲ませることは避けてください。
- 食事を工夫する
- 食欲がない場合は、食べやすいように柔らかくしたり、温めたり、好むものを少量ずつ与えてみましょう。無理強いはせず、愛犬のペースに合わせてください。
- 痛みの管理
- もし愛犬が痛みを感じているようであれば、獣医師に相談し、適切な鎮痛剤を処方してもらいましょう。指示された用法・用量を守って投与してください。
飼い主としての心構え
- 愛情を持って接する
- 犬が最期の時を迎える際には、愛情を持って接することが大切です。穏やかな環境を提供し、安心感を与えることが犬にとって重要です。
- 獣医との連携
- 犬の健康状態に不安がある場合は、早めに獣医に相談することが重要です。適切な診断や治療を受けることで、犬の苦痛を軽減する手助けができます。
- 思い出を大切にする
- 犬との思い出を振り返り、感謝の気持ちを持つことが大切です。犬との時間を大切にし、愛情をもって過ごすことが、飼い主自身の心の支えにもなります。
- 最期の選択を考える
- 犬が苦しんでいる場合、安楽死を選択することも一つの選択肢です。この決断は非常に難しいものですが、犬の苦痛を和らげるために必要な場合があります。獣医と相談し、最良の選択をすることが重要です。
犬の死ぬ前の行動を理解し、適切な心構えを持つことは、飼い主にとって非常に重要です。犬との最後の時間を大切にし、愛情を持って接することで、犬にとっても飼い主にとっても穏やかな別れを迎えることができるでしょう。犬の健康状態に注意を払い、必要なサポートを提供することが、飼い主としての責任です。
愛犬との時間は、私たちにとってかけがえのない宝物です。最期の時まで、愛情を込めて接し、感謝の気持ちを伝え、穏やかなお別れができるよう心から願っています。もし、愛犬の様子に不安を感じた場合は、迷わず獣医師に相談してください。
| 2025.03.27 09:52 | |
| 2025.03.27 09:53 | |
| 知識・知見・学習 |
犬のしつけに困ったら…

- 料金が高額…
- 時間がない…
- 外出できない(したくない)…
- 適当な教室が見つからない(そもそも近くに教室がない)…
などの理由で、しつけ教室に通うことを諦めている方も多いかと思います。そんな飼い主様に紹介したいのが「しほ先生のイヌバーシティ」です。
イヌバーシティとは?特徴と魅力

しほ先生のイヌバーシティは、自宅で手軽に学べるため、時間や場所に制約のある方でも、ワンちゃんの問題行動を改善するための知識とスキルを身につけることができます。
しほ先生のイヌバーシティは、犬のしつけに関する幅広いトピックをカバーしており、具体的な指導方法や実践的なアドバイスが豊富に提供されています。
仔犬から成犬、犬種を問わず、全てのワンちゃんに対応できます。

しほ流しつけ術は、叩いたり怒鳴ったりしない「完全非体罰」の優しいしつけ方法です!
トイレトレーニングから無駄吠えの対処法、リードを引っ張らない散歩のコツなど、必ず覚えさせたい基本のしつけから、飛びつき・噛み癖など緊急性の高い問題行動の改善まで、さまざまなテーマを解決します。ぜひ一度、公式サイトを確認してみてくださいね。
しほ先生の略歴・経歴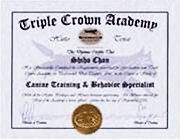
訓練士資格・行動学専門家資格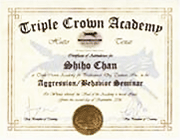
攻撃的な犬の行動学専門課程修了- 本名:飯島 志保(いいじま しほ)
- 米国トリプルクラウンアカデミー(現スターマークアカデミー)卒業
- 卒業生の中から優秀生徒として選抜、卒業後に指導者として同校勤務
- 訓練士資格・行動学専門家資格。攻撃的な犬の行動学専門課程終了
- 犬のしつけ施設兼ペットホテル「ワンコ・ワークス」代表
- NHK「プレ基礎英語」ドッグトレーナー出演
- 米国ペットグッズのポスターに、愛犬バスコ出演
- クエンティン・タランティーノ監督ハリウッド映画「デスプルーフinグラインドハウス」に愛犬バスコ出演
犬の訓練士養成校として世界有数の規模を誇るアメリカ・テキサス州のトリプル・クラウン・ドッグ・アカデミー(現スターマーク・アカデミー)で、犬訓練・行動学専門家の資格を取得し、卒業後ワンコ・ワークスを設立。これまでに受け入れた頭数は延べ3万頭を超える。

愛犬のしつけは飼い主さん自身ができるのが理想的!
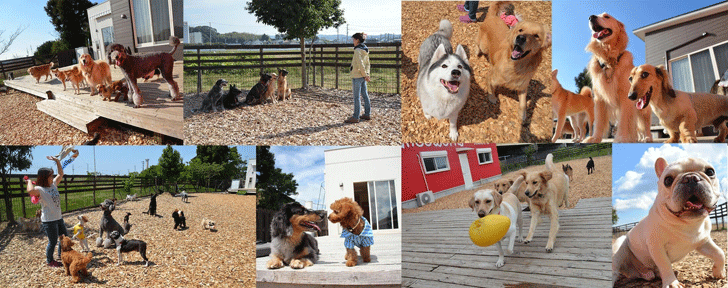
オンライン会員サイトで学習するため、パソコンだけでなくスマホやタブレットを使って、いつでもどこでもワンちゃんのしつけができます。
DVDや書籍の場合、教材が届くまで時間がかかりますので、今すぐスタートできませんが、イヌバーシティはオンライン教材ですので、購入後すぐにしつけを開始できます。

- 仔犬・成犬、犬種に関係なく対応できます。
- 体罰一切必要ありません。
- しつけの失敗シーンも堂々公開。
- 24回分割可(1日当たり30円以下)
イヌバーシティでは「犬をしつける方法=テクニック」だけではなく、飼い主様自身が「どのような思考で実践しなくてはいけないか」についても、しっかりフォローされています。



